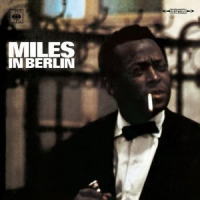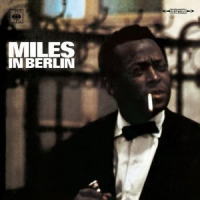|
モードでつくられたジャズのアルバムの事実上最初の作品で、モードジャズの代名詞となっています。それと同時に、ジャズ史上の最高傑作アルバムのひとつともいわれています。上でのべた2人、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーンと、キャノンボール・アダレイ、ビル・エヴァンスがアドリブソロを演奏します。
1曲目の「ソー・ホワット」を聴いてください。これまで聴いてきたジャズとはあきらかに違う「感じ」をいだくのではないかな? 緊張感はあるんだけど、つかみどころのない、どこかふわふわした不思議な感覚。
このアルバムが傑作であることに異論はないのですが、初めてのモードということでミュージシャンが手さぐりで演奏しており、そのため抑制が効いていて、その結果うまれた「不思議な」傑作なのではないかと思っています。
そのような感覚を与えるアルバムはこの後は現れておらず、特にマイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーンは、モードを完全に自分のものにすると、手にした自由度を「激しさ」という形で表出していきます。次にそのことがわかるアルバムを聴いてみましょう。
|